総研叢書
総研叢書 ― 隔年発行 ―
平成11年(1999)より従来の『布教資料』シリーズをリニューアルし、より広い視野で現代社会の様々な問題を積極的に取り上げてゆくために、当研究所の研究員が中心となって執筆・編集を行っている。
【これまでの刊行物】
第13集『つどう・やすらぐ・ささえあう―お寺での介護者カフェを通じて―』(2024年)
第12集『浄土宗僧侶生活訓―あるべき僧侶の姿を目指して―』(2022年)
第11集『いのちの選択に向きあうとき』(2020年)
第10集『それぞれのかがやき:LGBTを知る―極楽の蓮と六色の虹』(2018年)
第9集『僧侶、いかにあるべきか』(2016年)
第8集『浄土宗の「浄土三部経」理解』(2014年)
第7集『共に生き共に往くために』(2012年)
第6集 『よりそう心』(2010年)
第5集 『いのちの倫理』(2008年)
第4集 『念仏信仰の諸相』(2006年)
第3集 『寺院のインターネット利用』(2004年)
第2集 『法然上人とその門流』(2002年)
第1集 『"いのち"が危ない』(2000年)
第13集 つどう・やすらぐ・ささえあう―お寺での介護者カフェを通じて―(2024年3月発行)
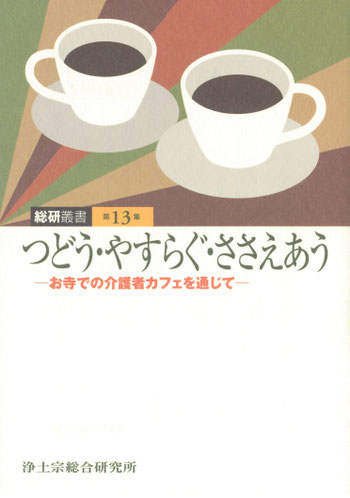
PDFファイル 【5.2 MB】
【目次】
第2章 浄土宗寺院における「お寺での介護者カフェ」開催の具体例/下村達郎
第3章 「お寺での介護者カフェ」主催者と参加者に見られる影響/伊藤竜信
コラム① 高齢者ケアにおける僧侶の関りへの期待―認知症ケアの最前線から―/岡村毅
第4章 「お寺での介護者カフェ」の地域を超えた連携の可能性/工藤量導
第5章 「お寺での介護者カフェ」の地域性に基づく展開/山下千朝
コラム② 寺院か取り組む介護者カフェの特色―僧侶へのアンケート調査から―/宇良千秋
コラム③ 読経で健康!プロジェクト~お経を唱える習慣がもつ可能性~/枝広あや子
【補論】浄土宗における社会貢献事業の歴史と教理的理解/東海林良昌
第12集 浄土宗僧侶生活訓―あるべき僧侶の姿を目指して―(2022年3月発行)

PDFファイル 【2.5 MB】
第11集 いのちの選択に向きあうとき(2020年3月発行)
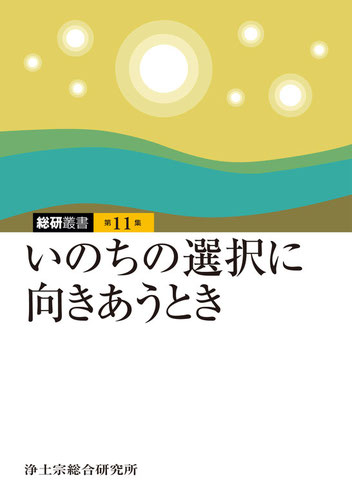
PDFファイル 【2.8 MB】
【目次】
第2章 安楽死について ―日本の動向と世界の現状/ 坂上雅翁
―現場での葛藤から/伊藤竜信
第4章 いのちの終わりにおける選択への向きあい/伊藤竜信・吉田淳雄
―不妊治療と生殖補助技術から考える/野村真木子
第10集 それぞれのかがやき:LGBTを知る―極楽の蓮と六色の虹―(2018年3月発行)

PDFファイル 【1.7 MB】
第9集 僧侶、いかにあるべきか(2016年3月発行)

PDFファイル 【1.8 MB】
第8集 浄土宗の「浄土三部経」理解 ―法然上人と親鸞聖人の相違をめぐって―(2014年3月発行)

PDFファイル 【1.2 MB】
【目次】
第7集 共に生き共に往くために ー往生と死への準備ー(2012年3月発行)

PDFファイル 【30.2 MB】
【目次】
・はじめに、問題の所在、臨終行儀について、法然上人の臨終の教え、おわりに―凡夫のための臨終の教え―
・はじめに、超々高齢社会とは、死を迎える場所の変化、延命治療の問題点、隠蔽される死 ポックリ信仰の意味は、尊厳死とは何か、終活ブーム
第3章 医療・仏教・死の現場―海外の事例が日本に示唆するもの―/ジョナサン ワッツ・小川有閑
・はじめに、日本における医療界の問題・仏教界の問題、死にゆく人のための仏教的ケア、インフォームド・コンセントと告知の問題、医療従事者や宗教者のコミュニケーション能力、仏教チャプレンとチームケア、病院・ホスピス・在宅ケア、グリーフケア
・ホスピスについて 日本でのホスピスについて 実践施設の概観、理念と実践内容の考察 共通する課題―医師・ビハーラ僧の声から見えてくるもの―、まとめ―僧侶として―
・エンディングノート成立と広がり、主な特徴や特殊な事例、実際の使用から見えてくる限界と「書く行為としての終末期への対応」、おわりに
・死生学など、日本人の死生観、宗教と医療、ビハーラ、ホスピス、スピリチュアルケア、闘病記、ルポ、エンディングノート、老いの準備、弔辞、グリーフケア、自死問題、生命倫理、その他―詩、エッセイ、漫画 絵本、映画
第6集 よりそう心 ―現代社会と法然上人―(2010年3月発行)

PDFファイル 【18.1 MB】
第5集 いのちの倫理 ―臓器移植・尊厳死・生殖補助医療―(2008年3月発行)

PDFファイル 【28.1 MB】
第4集 念仏信仰の諸相 ―法然上人とその門流Ⅱ―(2007年3月発行)
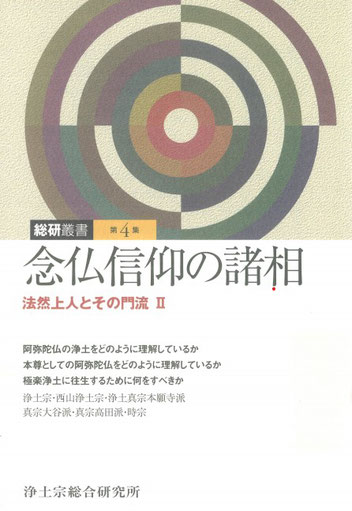
PDFファイル 【21.4 MB】
【目次】
第3集 寺院のインターネット利用 ―現代社会に対応する寺院―(2004年5月発行)

PDFファイル 【16.7 MB】
第2集 法然上人とその門流 ―聖光・證空・親鸞・一遍―(2002年3月発行)

PDFファイル 【25.9 MB】
【目次】
◎浄土宗(鎮西派)
◎浄土宗西山派
◎浄土真宗
◎時宗
第1集 "いのち"が危ない ―現代社会の諸相と課題―(1999年12月発行)

PDFファイル 【17.1 MB】
